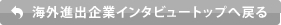―海外に進出する企業は、人材のマネジメントについて苦労することが多いようですが、御社ではいかがでしょうか?
お恥ずかしい話、弊社でも人材マネジメントはかなり苦労していて、周りの飲食店同様、離職率も高いです。ときには、正社員で採用した人間が2週間で音信不通になったり、アルバイトスタッフが数日で辞職してしまうこともありました。幸い、早い段階で右腕となるローカル社員が見つかり、なんとか店舗運営できていますが、もしも見つかっていなかったら、まともに運営できていなかったかもしれません。―どんなところに苦労されるのでしょうか?
一番の課題は、私が店舗のマネジメントになかなか時間を割けないということです。言い訳になってしまいますが、各国へのフランチャイズ展開を推進するため、かなり頻繁に海外へ飛んでいるため、シンガポール国内の店舗や従業員へのケアが十分できていません。ここに関しては、一刻も早く体制を整えていこうと思っています。それ以外の部分で難しいのは、やはり日本との文化や考え方の違いでしょうか。
―わかります。弊社は東南アジアで勤怠管理システムも提供していますが、特に時間に関する考え方が日本人とは異なりますよね?
違いますね。例えばシフトが9時からだった場合、9時に到着して、そこから着替えたり準備を始めるスタッフが多くいました。他にも、決まって3分くらい遅れてくるスタッフだったり。今でこそなくなってきましたが、口うるさく勤務時間には働く格好で店頭にいるよう伝え続けたり、勤怠管理システムを導入したり、様々な施策を打つことで、一つ一つ直してきました。―勤怠管理システムを入れているのですね。オーバータイム(残業)はどのように管理しているのですか?ローカルスタッフの場合、オーバータイム分の給与もシビアに求めてくるかと思いますが?
オーバータイムは難しいですね。勤怠管理システムで管理して、もちろん残業代も支払っています。ただ、日本と違ってモチベーションなどの違いにより、個々の生産性が大きく異なるため、単純に残業時間分を払うわけにもいきません。モチベーションが低く、ゆっくり働いているスタッフに対して残業代を支払えば、真面目に生産性高く働いているスタッフたちにとっての不平不満につながってしまうでしょう。―確かに、できるだけ働かずに給与を得たいと考える従業員は少なくないように感じます。そのあたり、御社ではどのように管理していますか?
弊社では、各業務の生産性について基準値を設定しています。例えば、パンの生地を作る業務は、1時間で何十個、といった具合です。その基準値以上の生産性で、勤務時間を超過した場合はオーバータイムを認めています。 もちろん、それだけでは判断しきれない追加業務が発生することもあるので、マネージャーの承認があれば、例外のオーバータイムも認めています。働いて頂いた分はきっちり報酬として支払うのが前提ですが、その中でも優秀なスタッフ、頑張っているスタッフが、損をしないような仕組みを作っていきたいです。―シンガポールやアジアの従業員を雇用されているかと思いますが、日本人の従業員と異なると感じることはありますか?
スタッフと接していて感じるのは、日本人よりもキャリアプランへの意識が強いことです。具体的にキャリアプランをイメージできている人が多いわけではありませんが、将来を描いた上で、どんなキャリアを進むかは必死に考えていると思います。だからこそ、給与や待遇に関して、良くも悪くも、非常に気にしている人が多いです。 特に昇給への認識は日本と大きく異なり、昇給の時期に昇給しないことは、不要な人材とみなされた、いわゆる肩たたきのような認識に近いものがあります。アジアは経済全体が成長し続けているため、働いた期間が伸びれば給与も自然と上がる、という認識が強いのかもしれません。
最後に、今後の海外事業の展望があれば教えてください。
直近では、オーストラリア、カナダへのフランチャイズ展開が決まっていて、今年中にマレーシア、インドネシアへの展開もできればと思っています。だからこそ、海外事業を管理するチームを作っていこうと思っています。 これから更に海外事業を更に拡大するには、マネジメント体制を組織化し、人を育てていく必要があると感じています。マネジメント制度、評価制度も含め、スタッフたちの働く気概や意味などを醸成できるような会社にして行きたいです。 弊社の日本側では既に人事制度が整っていますが、日本の制度をそのまま適応してもあまり機能しないことはわかりました。私自身も、まだまだ現地のことは理解しきれていませんし、こちらのやり方を押し付けるのではなく、まずは従業員との対話から、この国に適した形を模索していこうと思います。(終)記事の監修

| 日本でクラウド勤怠管理システム「KING OF TIME」を開発し、国内シェアNo1を獲得したメンバーが、その海外展開として東南アジアへ進出。徐々に人事管理が浸透してきている東南アジアでも勤怠管理システムや人事管理システムを提供し、ローカル企業のクライアントも多数獲得。 |